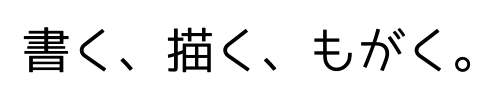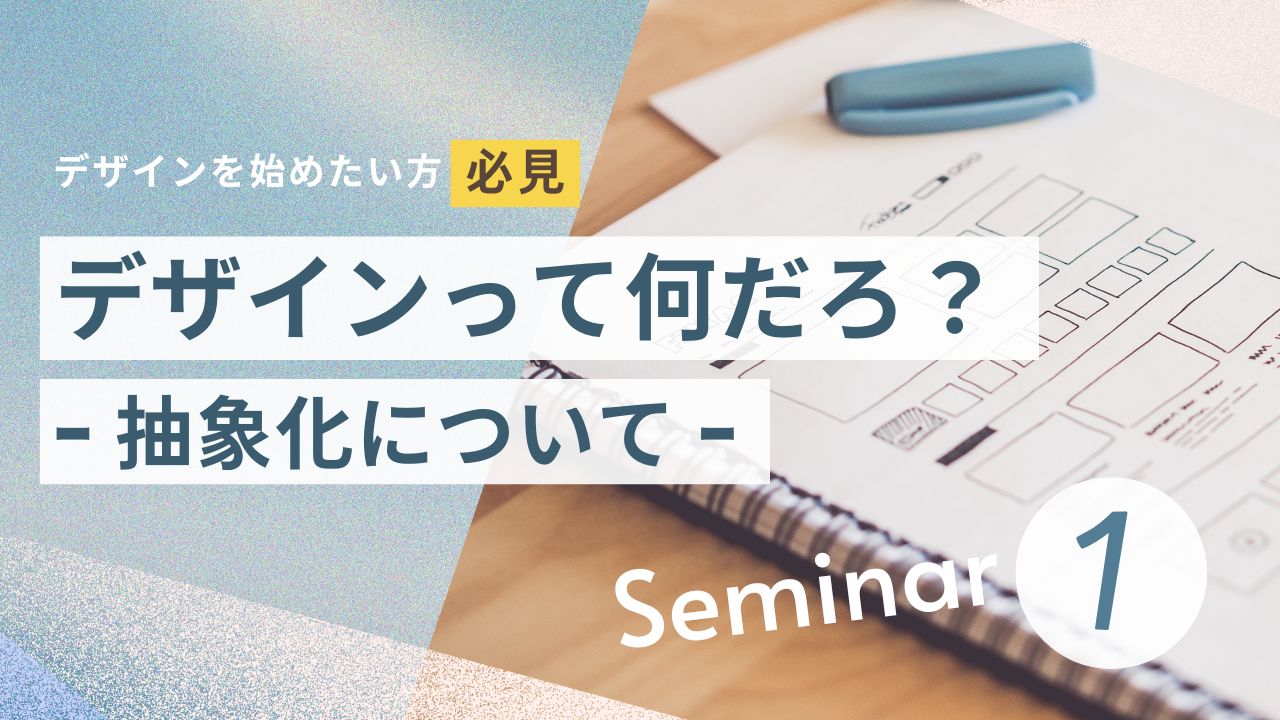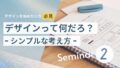こんにちは。
【書く、描く、もがく。】管理人のmizeです。
本日は、デザインって何だろう?と考える回です。
実はわたくし、美大を出たわけでも専門学校を出たわけでもないので、そんな座学を聞いたことは一度もありません。
いまのWeb制作会社に運よく就職できて、素人から実戦で活躍できる人材になれた…ただそれだけなのです。(人生一期一会とよく言ったもので、その話はまたいつか…!)
主に先輩や社長から教わり、その他は独学でした。本を読んだりネットを見たり…。
そんな私が学んできたことをもとに今回は書いていきますので、お時間あればさらっと読んでみてください。
デザインとアートの違い
まず、「デザイン」と「アート」について考えてみます。
「デザイン」と「アート」はよく混同されがちですが、実は大きく異なります。
アート
「アートは基本的に「自己表現」を目的とし、制作者の感性やメッセージが自由に表現されるものです。」とChatGPTは教えてくれました。
ゴッホとかの絵画なんですかね。建築でも「ん…なんじゃこりゃ?」なんて素人の私は思ってしまうもの、それをアートでくくっています。
例えば、アートなポスターは、見る人に自由な解釈を促し、正解は見た人それぞれで良いということになります。
デザイン
一方で、「デザインは「目的達成のための手段」として存在し、情報を整理し、見る人に伝わりやすくすることが重要です。」とChatGPTは言います。
インスタの広告バナーや街で配っているチラシなんかがそうなのではないでしょうか。
先ほどの例と同じポスターで言うと、デザインされたポスターは、商品の魅力やイベント情報を的確に伝える役割を果たすべきツールだと私は思います。
つまり、アートは「感じること」を目的とし、デザインは「伝えること」を目的としています。
具体と抽象について
次にお伝えしたいのが、具体と抽象です。
日常生活における抽象
先にお伝えすると、抽象化とは「共通点を抜き出してシンプルな概念にすること」です。
これが日常生活だとどういった事かと言うと、「具体的な手順を省き、本質的な目的や方針を伝えること」です。
例えば話すときに「それだと抽象的すぎて分からない」や「もっと具体的な案をだして」等のようなやりとりってよくありますよね。
子供とのやりとりでもよくよくあります…。道で会った知らないおばちゃんに「これね、〇〇ちゃんがねわたしの誕生日にくれたんだよ!」とヘアゴムを見せたとしても、おばちゃんからしたら「だれじゃいその子、誕生日しらんし!」って思うと思うんです(こんなお母さんでごめんなさい(笑))。
そこは「おともだちにもらったんだよ」だけで良いですよね。
なので、日常の中で、話す相手によってその抽象度って変わってくることが分かります。
仕事の指示もそうです。仕事できる人に対して「あれをこうしてこうして、ここをこうして、〇〇さんに一回確認して、あれとあれを添付して、、、うんぬんかんぬん」って指示しないと思います。
指示を出す側の人も具体的な手順を省き、本質的な目的や方針を伝えることで相手が理解できることもあるんですよね。
ここで重要なのが!指示出す側と受ける側のその度合いによって、仕事のスピードや質が全く嚙み合わなくなってくるということです。
以下のように4パターン考えられます。
- 抽象度高い指示役 × 抽象度高い受ける側
- 抽象度高い指示役 × 抽象度低い受ける側
- 抽象度低い指示役 × 抽象度高い受ける側
- 抽象度低い指示役 × 抽象度低い受ける側
1番上はお互い多く語らなくても円滑に業務遂行できると思います。
1番下は…想像するだけで恐ろしい気がします。
日常生活におけるこのバランスってめちゃくちゃ大事ですよね。夫婦もまた然り…。
デザインにおける抽象
長くなってしまったので、デザインの話に戻ります。
デザインにとっての抽象化とは先ほどお伝えしたように「共通点を抜き出してシンプルな概念にすること」です。
具体的な情報だけでは説明的すぎてつまらなくなりますし、抽象的すぎると何を伝えたいのかわからなくなります。
例えば、企業のロゴデザインを考えると、シンプルなマーク(抽象)と会社名やスローガン(具体)が組み合わさって初めて効果的なものになります。良いデザインは、必要な情報を整理し、伝えるべきものをシンプルに表現することが求められます。
リンゴ屋さんからロゴを依頼されてりんごと屋号名いれただけでは、とうてい”デザイン”とは言えないんですよね。
「では一体どうすんだい?」
それはまた次回お伝えするとしましょう。長くなってしまったので今回はこれで。m(__)m